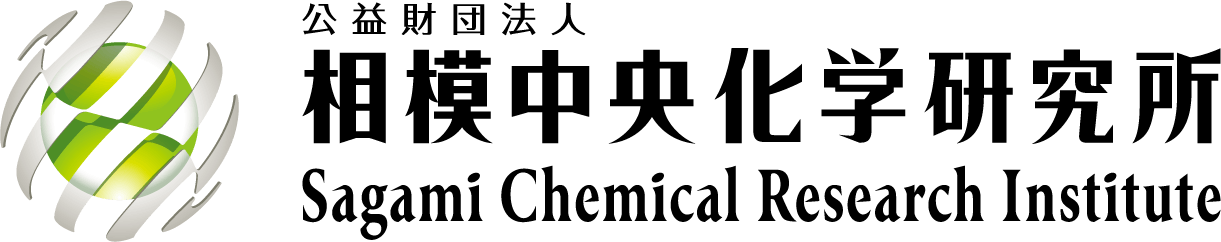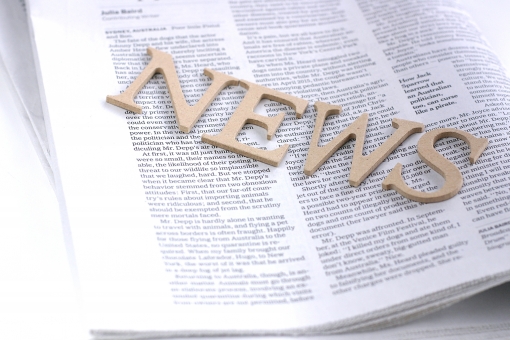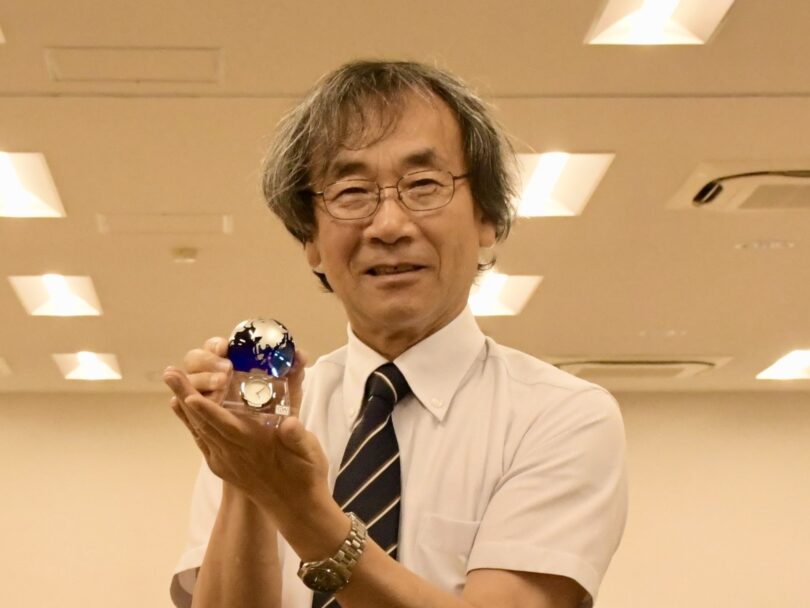所長から皆様へ
事業概要
研究の目的
有機合成化学により社会発展に貢献可能な物質とその製造方法を創出する
 本研究所は、保有する先端的技術シーズや研究機能を広く社会に還元すべく、化学産業の持続的な成長や国際競争力強化に繋がる実践的技術/イノベーションの創成的開発研究と、新しい学術分野の開拓を目指して長期的視野に立って推し進める核心的基礎研究を両輪とし、これをバランスよく推進する研究機関であることを目指しています。
本研究所は、保有する先端的技術シーズや研究機能を広く社会に還元すべく、化学産業の持続的な成長や国際競争力強化に繋がる実践的技術/イノベーションの創成的開発研究と、新しい学術分野の開拓を目指して長期的視野に立って推し進める核心的基礎研究を両輪とし、これをバランスよく推進する研究機関であることを目指しています。国際的に経済安全保障の重要性が指摘される中、持続可能な経済社会の実現へ向け、気候変動並びにエネルギー対策を一体のものとしての強化する必要があり、本研究所は、これらの潮流変化を的確に捉え、産業及び学術の進歩・発展に資する有用物質の創製・協創、並びにそれら有用物質の効率的な製造技術の開発をもって応えなければなりません。DXやビッグデータの活用に資する第5世代移動通信システム(5G)の商用利用が開始され、産学界では既に次世代の第6世代移動通信システム(6G)の研究開発が始まっています。これら次世代システムで要求される高度な電気的・光学的特性を満たす新しい有機電子材料や高分子材料、またIoT技術の普及により多様化するユーザーインターフェースに必要となる各種センサーや表示用有機機能性色素などの創製が不可欠です。また、カーボンニュートラルの観点からは、CO2の排出抑制並びに有効利用(リサイクル)を両輪として推進する必要があり、CO2排出抑制のため導入が加速している電気自動車(EV)向けリチウムイオン電池用添加剤や新しい再生可能エネルギー源である有機系太陽電池用材料の開発、カーボンリサイクルの取り組みとしてはポリマーの化学的再生方法や炭素固定反応用触媒の開発推進が望まれています。本研究所では、長年にわたり蓄積してきた有機合成化学、特にπ共役・複素環化合物の合成技術及びフッ素化学に関する高度な知見を活用し、これらの課題に精力的に取組みます。
また、π共役・複素環化合物及びフッ素化学分野を本研究所の研究開発力を最も発揮することのできる重点研究領域と定義し、ここに研究資源を集中的に投資することで、目先の利益に捕らわれず独自の技術シーズ及び学際的成果の創出を追求する核心的基礎研究を推進していきます。
革新技術の創出は、純粋な好奇心と探究心に基づく基礎研究のみならず、成果に対する社会的責任に裏付けられた開発研究によってもたらされるものです。本研究所は、基盤とする有機合成化学における研究能力を存分に活用する一方で、生産設備面、製品評価面、原資面での不足を補うために広く産業界と連携を深めながら、日本の産業及び学術の進歩・発展に資する有用物質、並びに有用物質の効率的な製造技術を創製に貢献することを事業方針といたします。
令和5年7月1日
常務理事 所長 井上宗宣
公益目的事業
研究に関する事業
研究事業は本研究所が掲げる公益目的事業の基軸となる事業です。新しい学術分野を切り開く独創性のある学術研究及び今後の社会ニーズに応え得る科学技術の開発研究を本事業の目的としています。
研究事業
本研究所は単なる既存の知識の組み合わせによる技術の改良や学問的追究のみに終わる研究ではなく、化学工業に有用な原理的あるいは革新的な化学技術の発見、発明を指向した研究を行っております。
共同研究事業
本研究所で見出した化学技術を社会ニーズに直結した実用化技術へと成熟させるために、広く産業界との共同研究を積極的に実施し、研究成果の早期の結実を目指しています。また、研究員を相互に派遣することで市場ニーズや技術課題の共有化を深め、工業化のための効率的な共同研究を推進しています。
研究成果等を広く一般の利用に供する事業
広報事業
本研究所で生まれた新しい研究成果は、逸早く特許出願や新聞発表、学会発表、学術論文投稿等を通じて社会に公開し、科学技術の発展や学術の進化への貢献を目指しています。
技術交流事業
研究開発の学術的な質の向上と科学的な深化を進めるために、著名な研究者による講演会や定期的な学術セミナー等を開催し、大学や産業界の多分野の研究者や技術者との意見・情報交換の場を提供することで、最新の学術・技術情報の共有化を図っています。
- フッ素相模セミナー(毎年6月開催)
- 材料相模セミナー(毎年10月開催)
- 農薬相模セミナー(毎年1月開催)
- 高分子相模セミナー(毎年12月開催)
技術ライセンス並びにコンサルティング事業
本研究所で生まれた新しい化学技術は、産業界から要望があれば可能な範囲でライセンスいたします。また、蓄積した知見や技術を産業界に役立てるため、所外からの要請に応じて、分析・試験等を含む化学技術に関するコンサルティングを行います。
人財育成に関する事業
自然科学の分野における国際競争力を高め、質の高い研究成果を創生するための基盤は「人」であり、創造性豊かで挑戦意欲を持った研究者を育てる人財育成事業も、本研究所の重要な公益目的事業の一つです。また、近隣の大学等から卒業研究生や大学院生、インターンシップ学生を受け入れ、主に化学に関わる基礎から高度な専門的研究に関する教育及び研究指導を行うとともに、本研究所の研究員を非常勤講師や連携教員として派遣することで、大学等での高等教育の一翼を担っています。(学生募集)